2025.05.13
【導入事例】保険業界だからこそ、万が一を未然に防ぐ取り組みを。地域発信で加速する、日新火災のサステナビリティ
日新火災海上保険株式会社(以下、日新火災)様は、創立110年を超える東京海上グループの損害保険会社。全国各地に支店を構え、お客さまに最も身近で信頼される損害保険会社を目指されています。
そんな日新火災様に、2023年に戻り苗をご導入いただきました。最初は田辺サービス支店でご導入いただき、田辺サービス支店の皆様の発信で全国へ広がり、今では累計約70本の苗木が育っています。
保険といえば、万が一事故や災害にあった時に備えるもの。いわば、事後の安心を与えてくれるものです。ですが、「万が一」は起きない方がいい。日新火災様はそんなお考えの元、様々なサステナビリティに取り組まれています。
今回はそんな日新火災様に、サステナビリティのお取り組み内容や、戻り苗の導入背景・ご感想などをお伺いしました。


日新火災が取り組むサステナビリティ|事後の安心だけでなく、未然に防ぐ安心を。
ー 日新火災様はサステナビリティに向けて、これまでどのような取り組みをされてこられたのでしょうか。
折原様:
私たちは、サステナビリティは「経営理念の実践」そのものであるととらえ、「東京海上グループサステナビリティ憲章」に基づきサステナビリティを徹底的に実践してきました。
その1つが、「MOTTAINAIキャンペーン」です。これは、ワンガリ・マータイさんが1977年から非政府組織(NGO)として始めたケニアでの植林活動です。環境保全にとどまらず、植林を通じて貧困からの脱却、女性の地位向上、ケニア社会の民主化にも大きく寄与しています。私たちも、売り上げの一部を寄付することでグリーンベルト運動に参加しています。
また、2023年には北海道厚真町と「復興・地方創生に向けた連携協定」の締結をしました。厚真町は、2018年に胆振東部地震で被災した町です。多くの森林に恵まれた場所であることもあり、未だ、土砂災害により崩壊した森林の再生や防災・減災に向けた備え等の課題を抱えています。保険というのは、それぞれの地域と密につながっていくものでもあるので、このような取り組みも積極的に行っています。
北海道厚真町と日新火災海上保険株式会社との「復興・地方創生に向けた連携協定」の締結
https://www.nisshinfire.co.jp/news_release/pdf/news231213.pdf
ー お取り組みの中で大事にされていることはありますか。
折原様:
保険というのは、何かあったときに保険金という形でお客様に安心をお届けするものです。もちろんそれも大事ですが、事故や災害を未然に防ぐこともとても重要です。「万が一」の後に安心をお届けする保険業界だからこそ、「万が一」を防ぐことにおいても安心をお届けしていきたい……そう思っています。
そのような思いから、昨年にはヘルメットのリサイクルプログラムも開始しました。一般的に、ヘルメットの耐用年数は3~5年と言われています。そこで、定期的に回収し、交換・リサイクルすることで事故防止の啓発に繋げています。
テラサイクルとともにヘルメットのリサイクルプログラムを開始
~ヘルメットのリサイクルによる事故防止の啓発と循環型社会への寄与~
https://www.nisshinfire.co.jp/news_release/pdf/news241008.pdf
ー noteでの情報発信もされているのを拝見しましたが、こちらはどのようなものなのでしょうか。
約3年前より、日常で簡単にできるサステナブルなアクションを紹介しているサステナブルな情報メディアとして「日新火災 withCaNday」を立ち上げました。保険のご契約者様にかかわらず、広くステークホルダーの皆様に気軽にできるアクションをお届けしていくことで、「万が一」の前にも安心を届けていきたいと思っています。
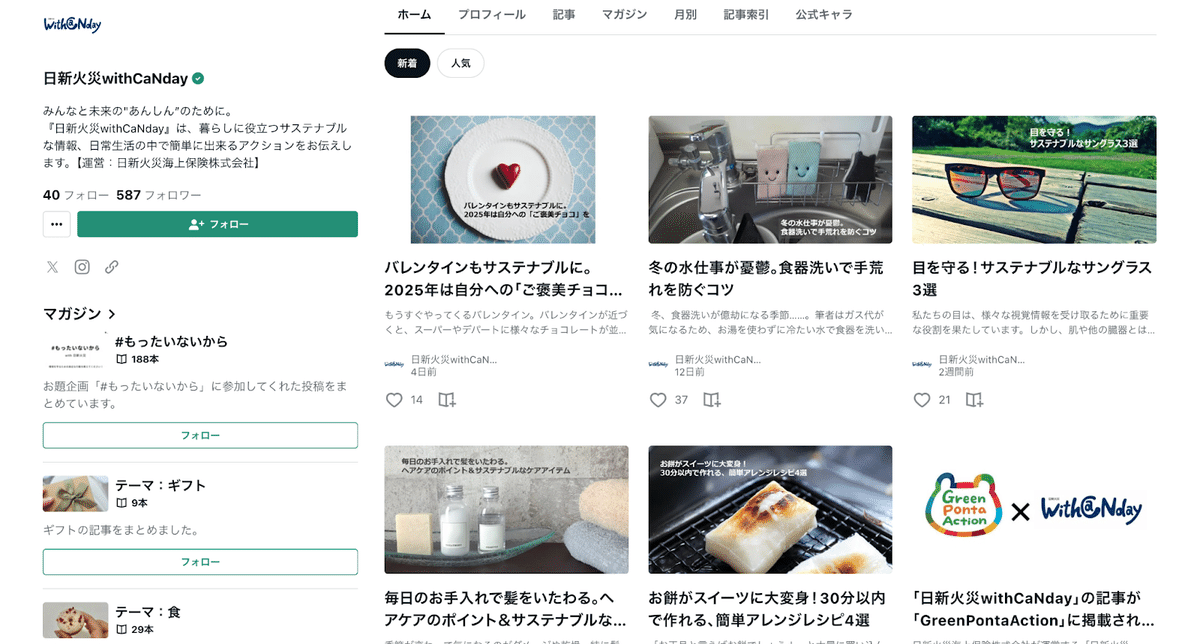
「戻り苗」導入のきっかけ|100年企業だからこそ、新しいビジネスと連携する。
ー 日新火災様の中で最初にご導入いただいたのは田辺サービス支店さまでしたが、ご導入のきっかけはどのようなことだったのでしょうか。
三瀧様:
日新火災では、現在全国各地の支店で戻り苗を育てていますが、和歌山県田辺市にある田辺サービス支店から始まりました。地元紙「紀伊民報」でソマノベースさんを見たのがきっかけです。

会社としても社会課題の解決に積極的に取り組んできましたが、まだまだ足りません。継続的に取り組む必要があるからこそ、楽しんでやれること・興味を持って取り組めることはないかと探していた中で、育てる・植えるというわかりやすい循環を育むことに、楽しみながら参加できる戻り苗を知りました。

戻り苗がかえるのは田辺の山。私たち田辺サービス支店は、田辺の方々に必要としていただいています。私たちも、この町のため、皆様のためにできることをしていきたい。これなら、地域に貢献ができると思ったんです。
また、昔からある保険会社だからこそ、新しいビジネスともつながっていきたい。そして、この取り組みがハブとなり、様々なお客様・地域・企業の方ともつながっていきたい。そんな思いも重なり、本部に提案をし、導入が決まりました。
社内での「戻り苗」の広がり|1つの支店から、全国へ。
ー 田辺サービス支店からはじまり、今では十数支店で戻り苗にご参加いただいていますが、その背景をお聞かせください。
内田様:
田辺サービス支店での導入後、三瀧さんが社内ニュースとして戻り苗の取り組みを発信したり、ソマノベースの奥川社長と社内向けの対談イベントを実施させていただいたりしたんです。
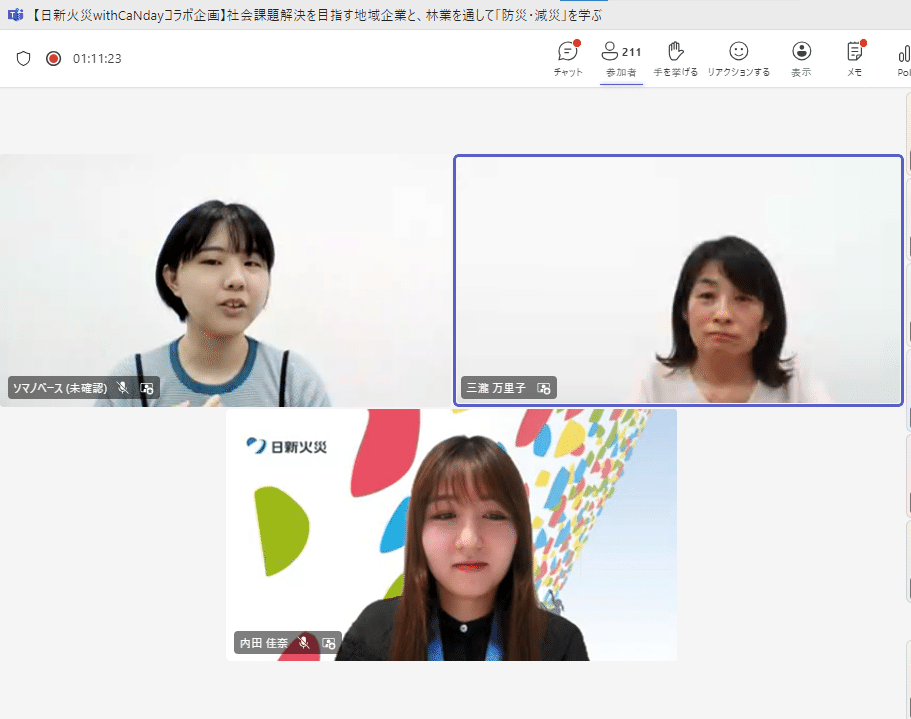
その反響で「うちの支店でも戻り苗を育てたい」という声が集まり、田辺サービス支店から始まった弊社での戻り苗の取り組みですが、現在は十数支店で戻り苗を育てています。
社員からの発信であったことで親近感を持ちやすいことに加え、戻り苗のわかりやすさや緑というオフィスにあって欲しい存在であることもあいまって、参加しやすかったのではと思っています。
ー 今や全国各地でご参加いただいている戻り苗ですが、実際にご参加いただいていかがですか。
三瀧様:
今では、戻り苗はコミュニケーションツールになっていますね。
田辺のお客様からすると、戻り苗で育てるウバメガシのどんぐりは馴染みのあるものなんです。ウバメガシは和歌山県の木であり田辺市の木でもありますから。でも、防災や山作りへの関係はあまりご存知でない方も多いので、戻り苗は改めて森林や防災について考え直すきっかけになっています。
また、社内でも様々なやりとりが生まれました。苗木はほったらかしで育つものではありません。日々様子を見ながら、お世話することが必要です。つまり、それぞれが主体的に関わったり、協力したりすることが大事になります。結果として、組織力が育まれ、試されているような感覚もありますね。
内田様:
どんぐりを育てている拠点でグループを作って月一でどんぐりの状況を報告しているのですが、内容からそれぞれの支店の個性を感じてます。声をかけている支店もあれば、直射日光を防ぐためにフェードをつけている支店もあります。
生き物なので育てる際に四苦八苦することもありますが、皆さん楽しそうで、社内を明るい雰囲気にしてくれていると感じますね。
日新火災が目指す、これからのサステナビリティ|地域発信の取り組みを全国へ。
ー 戻り苗をはじめ、様々なお取り組みをされていらっしゃいますが、これからどのようなお取り組みに発展させていきたいですか。
三瀧様:
日新火災は全国各地に支店があり、それぞれの地域に根ざしています。田辺サービス支店のある田辺市は土砂災害という課題に目を向け、ソマノベースさんという地域のパートナーに出会いました。同じように各地域にはそれぞれの課題や新しいアイディアで取り組む方々がいるはずです。
全国各地に支店があるからこそ、それぞれで地域の課題やプロジェクトを発掘して、連携して取り組んでいく循環を広げていきたいですね。
内田様:
それぞれの地域と深くつながっているのは、支店です。それぞれの支店が地域の声を集め、その支店の声を会社として施策にしていく。そんな流れをもっと生み出して、嬉しいニュースを広げていきたいと思います。今回の戻り苗も、そんな嬉しいニュースの1つですね。
折原様:
地域で考えて、地域とつながり、それぞれが自発的に取り組んでいく。これこそ、サステナビリティの取り組みにおいて欠かせないことです。戻り苗は、そんな事例になったと感じています。
田辺サービス支店がソマノベースさんとの取り組みを自発的に始めたように、他の地域にも同じように改めて地域に目を向け、地域と繋がっていくよう、伝播させていきたいです。
地域にはそれぞれ特徴があり、課題も取り組みのアイディアも異なります。私たちソマノベースも全国各地の様々な課題に取り組まれている方と、より協力を深め、取り組みを広げていきます!
戻り苗や森づくりに興味をお持ちいただいた方は、ぜひお気軽にソマノベース(info@somanobase.com)までご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
